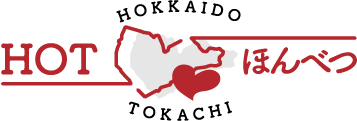SDGs未来都市に向けた本別町の歩み① – 官民連携のローカルSDGsの意義(未来創造課・山岡さんに聞く)

- インタビュアー
- 地域包括ケア研究所 藤井 雅巳
2024年7月に公表した北海道・本別町の「SDGs未来都市宣言」。北海道ではまだ6か所目であるこのSDGs未来都市に向けた歩みには、様々な問題意識とこれからを志向する本別町役場の想いが込められていた。
これからどんなことが始まるか目が離せない本別町の歩み。役場職員として本事業のど真ん中にいる未来創造課・課長補佐の山岡裕幸さんに聞いてみました。
(インタビュー実施 2025年1月)

山岡裕幸(やまおか ひろゆき)
本別町生まれ。中学校から関東で学生時代を過ごし、両親の故郷でもある本別町にUターンし、本別町役場に就職。教育委員会などを経て、2023年より未来創造課未来創造担当として着任。
SDGs未来都市を目指したきっかけ
–もともとどういうきっかけでこの事業が始まったのでしょうか。
山岡裕幸さん(以下「山岡」):まず前提として、世界的な規模で2050年にカーボンニュートラルを達成するという“脱炭素”の取り組みを行政としてやらなくちゃいけないことと、2030年にSDGsの17のゴール達成をしなければならないという世界レベルでもやらなくてはならないことが重なっていて。
これらの2つの要素がある中で、脱炭素だけの目的だと、再生エネルギーや蛍光灯のLED化や太陽光パネル設置とかにより、再生可能エネルギーを導入していきましょうということになり、取り組み自体が目的化してそこで終わりになってしまう。だから、街づくりにどういうふうにつなげていけるかっていうのが、見えてこなくて、役割として任せられたときに「面白くないな」って思ったんですよね。
だから、どうせやるなら街づくりにもつながる町としてストーリーのある計画づくりをしなくちゃいけないということで。街づくりにその要素を取り入れるためにも、目前のSDGsの2030年のゴールをまず目指し、その先の20年後の脱炭素、カーボンニュートラルの達成までを結び付けた方がいろいろなものがつながっていくので、いいんじゃないかと考えて。それで、SDGs未来都市計画っていうのを策定しようってなりました。
–初めに、そのような構想を考えたのっていつ頃なのでしょうか?
山岡:2023年の6月に専門事業者のアール・エ北陸さんと協定を締結し、その中でいろいろなノウハウを教えてもらって。まずは、町全体の意識の醸成から図らなくちゃいけないんだってことが分かりました。
はじめは、町職員や農協の職員、いろんな団体を巻き込んでカーボンニュートラルのカードゲームをやったりしました。また、2023年10月のKIDAKE(ツリー・フェスティバル)では、町民の意識調査などをするために、クイズ形式のワーク・ショップなどを行いアンケートなどを行ってきました。
アンケートなども踏まえて、町の皆さんの意識の醸成を図るには、みんなが関わっていける計画を作り、想いを共有しながら町づくりにも反映させていく方がいいと感じました。
その翌2月にSDGs未来都市の申請の公募がはじまるので、未来都市の選定を目指して、街づくりに落とし込みながらSDGsを意識して計画を作ってみようかという話の流れになりました。
その後、2月に計画申請をして、2024年5月に選定を受けました。その後、審査委員の質問に答えて反映させたものを7月に正式な計画として公表しています。

(写真)SDGs未来都市選定証授与式にて
SDGs未来都市の具体的な内容
-SDGs未来都市の計画は具体的にどのようなことを予定しているのでしょうか?
山岡:SDGsでは、経済、社会、環境の3つの分野・要素を循環させるっていうのが理念なんですよね。どれか一つかけても持続可能なサステナブルな世界にならないということで。そのためのゴールとして17のゴールが掲げられています。
それで、本別ではまず「経済」という視点から街を発展させ、そこを起点に「社会」や「環境」に波及させたいっていう流れになっています。重点項目としては全部で4つの項目を想定していて、これらをまず重点的に取り組んでいく予定です。

(出典)本別町SDGs2030年のあるべき姿
–なるほど。まずは「経済」に着目するということですが、どのあたりがポイントなのでしょうか。
山岡:まずは,サテライトオフィスを作って域外から企業が関われる流れをつくり、そこと域内ですでに様々な取り組みをしている人たちとの相乗効果で新たな事業を創発させることを企図しています。
–本別町にはすでに地元の農家が開発したレンチンだけで食べれる北海道十勝ポップコーンや本別高校の「とかち創生学」から生まれた本高フィナンシェなどすでに様々なおもしろい取り組みをしている人たちがいますよね。
山岡:そうなんです。そのような既に域内にある素材を活かすために、意図的に仕掛けるためのサテライトオフィスという場が必要だろうと。あと、SDGsブランド認証制度というのを定め、地域に存在するSDGsのゴールに関わる取り組みをしている商品などを認証することを考えています。
例えば100円の売価のフィナンシェがあるとしたら、そこに30円の上乗せ付加金みたいな形で、意識の高い方に130円で買ってもらい、30円は基金に積み立て、地域の課題解決や協力金として、いろいろな環境整備などに活用していく。本別公園の環境整備や、地域交通などの維持・活性化などの事業に充てるなどを予定しています。
–素朴な疑問なのですが、ブランド認証という付加価値はもちろん付く前提にはなると思うんですけど、100円に対して例えば30%?単純に値段が上がるみたいな話になると思うのですが、買う側も高いものを高い価格で買うということになると思うのですが、付加価値の話を除くと、単なる値段が上がるみたいになるのではないかと思いましたが。
山岡:なので、プロモーションとか絶対必要だと思うんですよね。単なる値上げにならないように、町としての選定されたSDGs未来都市というブランディングだったり、その未来都市である本別町でやっている農産物などを活かした地場産品を作りましたっていうストーリーがあってそこに共感を生み出すことが必要になります。ブランドロゴをつけて、パッケージなども変えて販売することを想定しています。
–そういうことですね。そうなった時に、このブランド認証を受けたものは、その協力金、基金の値段を込みにして売らなければいけない。じゃあ本当にそのブランドロゴに価値がないと、それが成り立たないってことですよね。
山岡:道の駅も専用のブースを作らなくちゃいけないと思うんですよね。そういうブランド品の選定などもふくめ、なかなか地元の現存の事業者だけだったら発想とかも含めてやりきれないと思うので、域外の事業者にサテライトオフィスなどの場を通じて関わって、新しい視点などを持ち込んでもらいたいと思っています。現在も、いくつか関心を持ってくれている大手の事業者なども視察などに来てくれています。
–参入する企業っていうのはどういうメリットがあるのでしょうか?
山岡:ある企業さんは、地域貢献の事業部隊がありCSR的な取り組みとして行っている場合もありますし、あとは町内では気が付いていない価値などを見出し、それぞれのプロモーション次第で、ちゃんと事業としても成り立つという見通しを立てていると思われます。まだ眠っている農作物や廃棄されているものなどを、新たな視点でうまく付加価値をつけられたら収益化が可能になってくるのではないでしょうか。
–そういうことですね。これも一つの差別化戦略ってことですね。単なるCSRだけだとちょっときついですよね。
山岡:3つ目の項目が「ゼロカーボンキャンプ場」です。
環境に関わる取り組みで,オートキャンプ場を今年作るっていう動きになっていたので、どうせ作るんだったら,ゼロカーボンでやろうと。 ゼロカーボンなどの要素があるようなキャンプ場で、意識の高い人たちに来てもらって,活用してもらえたらいいなと予定しています。
これも、ブランド認証制度を取ることも想定しています。

(写真)想いがこもり、熱っぽく語る山岡さん
–サービスでもブランド認証がとれるのですね。具体的にはゼロカーボンとしてどのようなことをキャンプ場で取り組むのでしょうか。
山岡:管理棟で消費する電力を太陽光で賄うとか、お湯を沸かすのに太陽光から熱をもらって沸かせるようにするとかのようなことを想定しています。
また、本別公園は交流人口が一番集まるところなので、そこで未来都市としての取り組みを域外の人にも知ってもらい、その人が集まる公園でSDGsの学習みたいなものがSTEAM教育などに活かせたらという考えています。本別には今専門人材がいるので、連携しながら看板を設置してSDGsコーナーみたいな10カ所を園内に立ててみようと。公園でいろいろなSDGsに関わる活動とか、取り組みに参加してもらって、それをシーズンごとに開催し、シーズン3回コンプリートしたら関連グッズを差し上げるようなことなど面白いのではないでしょうか。
–なるほど、それでは例えば、学校の教育現場に対して、SDGsを学べるフィールドがあるんですよみたいなふうにアピールすることもできそうですね。
山岡:そして、4番目が社会に関する項目で、中心市街地のリブランディングです。まさに今進行中の空き店舗を改装して,そこで新しい域外の事業者がチャレンジショップとしてやるっていうことが予定されているんですよね。
それを皮切りに、1年に1戸ペースで、閉まっているシャッターを開けて、街中に活気を増やしたいと。お店が開くことによって、新たな事業などが展開され、人の集まる“用事”を作っていくことができたらと考えています。
中心市街地を活性化させ、農村部の勇足とか、仙美里とか、美里別とかから、人が集まるようなきっかけを、考えながら、しかも効率よくつくっていく。これを、地域公共交通とうまく連動した取り組みとして推進していきたいと想定しています。
–なるほど。そういう意味では、交通の問題も含めて、街の都市機能の再編みたいな、そういう感じなんですか?
山岡:はい。すでに居住支援協議会というのが立ち上がって、空き家促進区域を設定するなどの取り組みを進めています。これは全国でも町村ではあまりないような取り組みが本別にはすでにあるんですよね。
–居住支援協議会は、なんで作ろうと思ったんですか?
山岡:居住支援協議会は、もともと高齢福祉の管轄部署が立ち上げたのですが、高齢者の住み換えなどをもともと想定していました。街中に空き家がありますので、農村部に住んでて、病院とかも通いづらい、一人で生活もしきれない、お子さんも帰ってこないような世帯を対象に、住み換えて町の中心部で生活すればいいのではないかという発想ですよね。
そのための、空き家調査などをしたりしてきていますが、私たちが意識しているのは、中心市街地の空き店舗で住み分けをしながらやっている、また、シャッター閉まっているところを開けて利活用する、リブランディングするということを目指しています。サテライトオフィスもそのなかにできる予定で、一体的に経済と社会の問題を解消できるといいなと考えています。
–なるほど。要するに高齢者の独居とか介護とか、見守りとかそういう社会の課題などともつながっていて、結局高齢者の人たちの交通手段がなくなると、市街地に来れなくなるから、生活が不便になってしまうので暮らしにくくなってしまう。
官民共同のローカルSDGs
山岡:本別町のSDGsの取り組みにおいて、肝となるのが「官民共同」ということなんです。結局、今の4つの事業を、行政が直営でやるのかといったら、やりきれないんですよ。
ブランド認証制度も、基金の積み立てといっても、一般会計に積み立てるの?みたいな話になってしまう。議会の承認を個別に全部得ていたら、結構、スピード感がなくなるじゃないですか。サテライトオフィスも直営でやるの?ってなったら、設置要項から使用条例定める必要があるのですが、自由が利かないので、誰も使う人いないよ、つまんない、ってなってしまう。
そこで、今回「官民共同のローカルSDGs」って副題をつけています。これまで、本別町民の感覚としては行政がやることが当たり前になってしまっているのですが、この意識を変化させたいという想いもあります。町の予算的な余力も限りがありますので。
–今、PFIなどの資金調達の在り方も含めて、民間の力を活用する流れになっていますよね。
山岡:そのため、中間支援組織(一般社団法人を想定)を設立し、そこと連携協定を結んで、基本的には民間主導の中間支援組織で運営してもらうというような建付けにしています。
中間支援組織は4人の地元の民間事業者さんたちが出資して会社を作ることになっています。完全に今までのフェーズとは、一線を画している、違う次元だと思うんですよね。
これまでは、全部行政が主導してしまっていたところがあるのですが、それを脱却したいっていう思いでやる予定です。だから「官民連携のローカルSDGs」ことこそがポイントなんだと思います。

(出典)経済・社会・環境の三側面の統合的な向上を促す「中間支援組織本別サスティナブルデザイン」の設置
–ありがとうございます。「経済」からはじまり、「社会」そして「環境」面に統合的につながっていく「官民連携のローカルSDGs」の取り組み。これからの動きから目が離せないですね。
取材年月:2025年1月