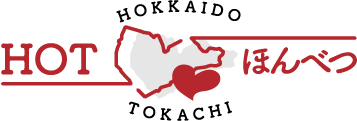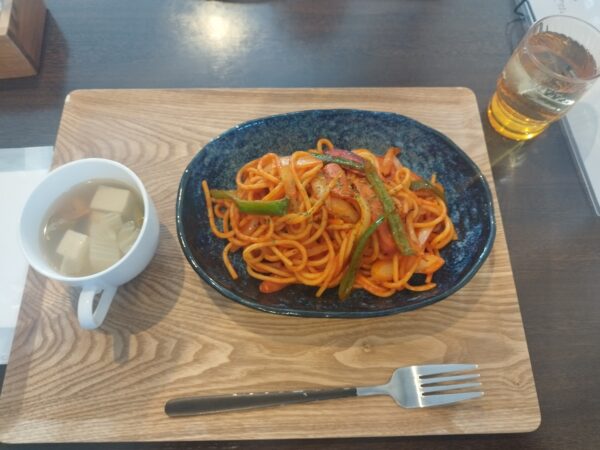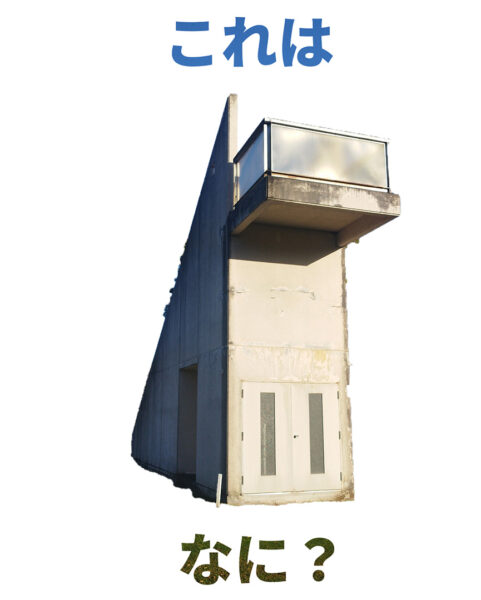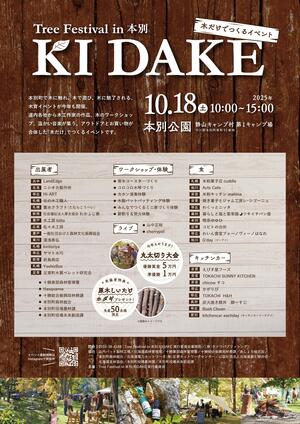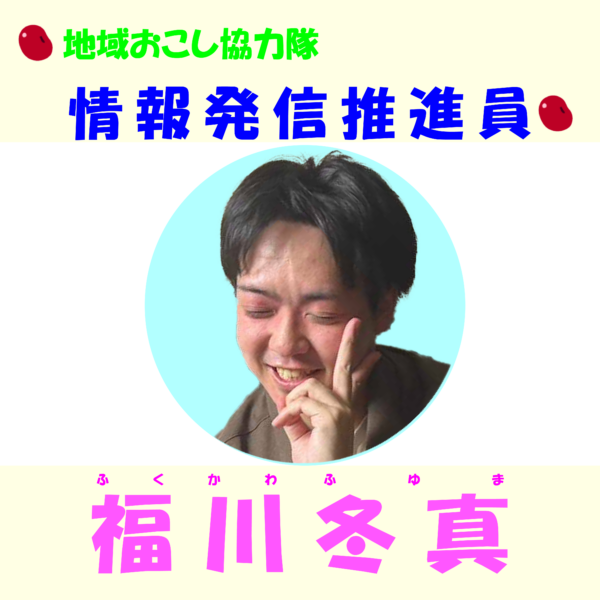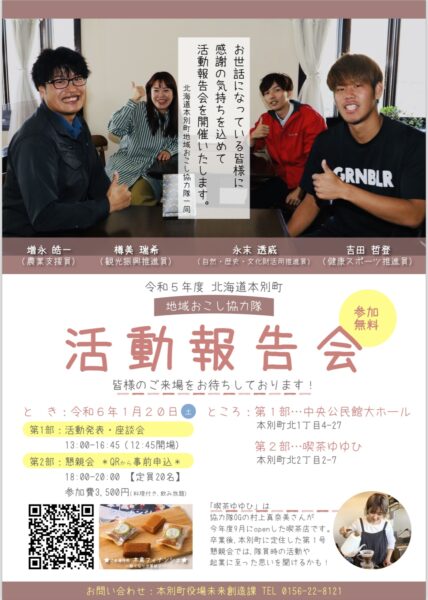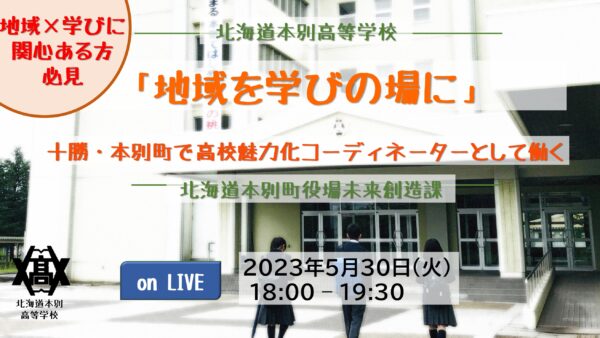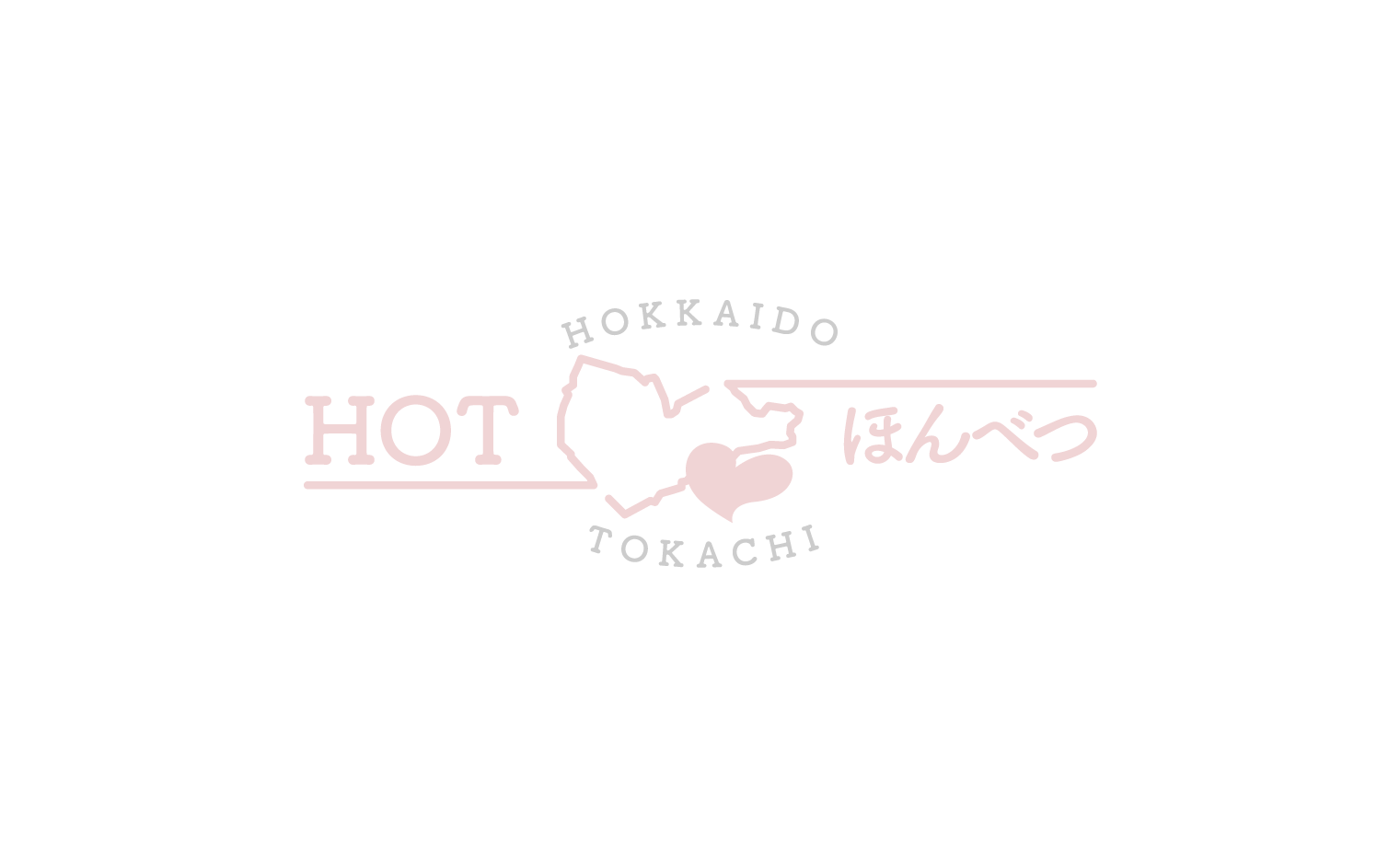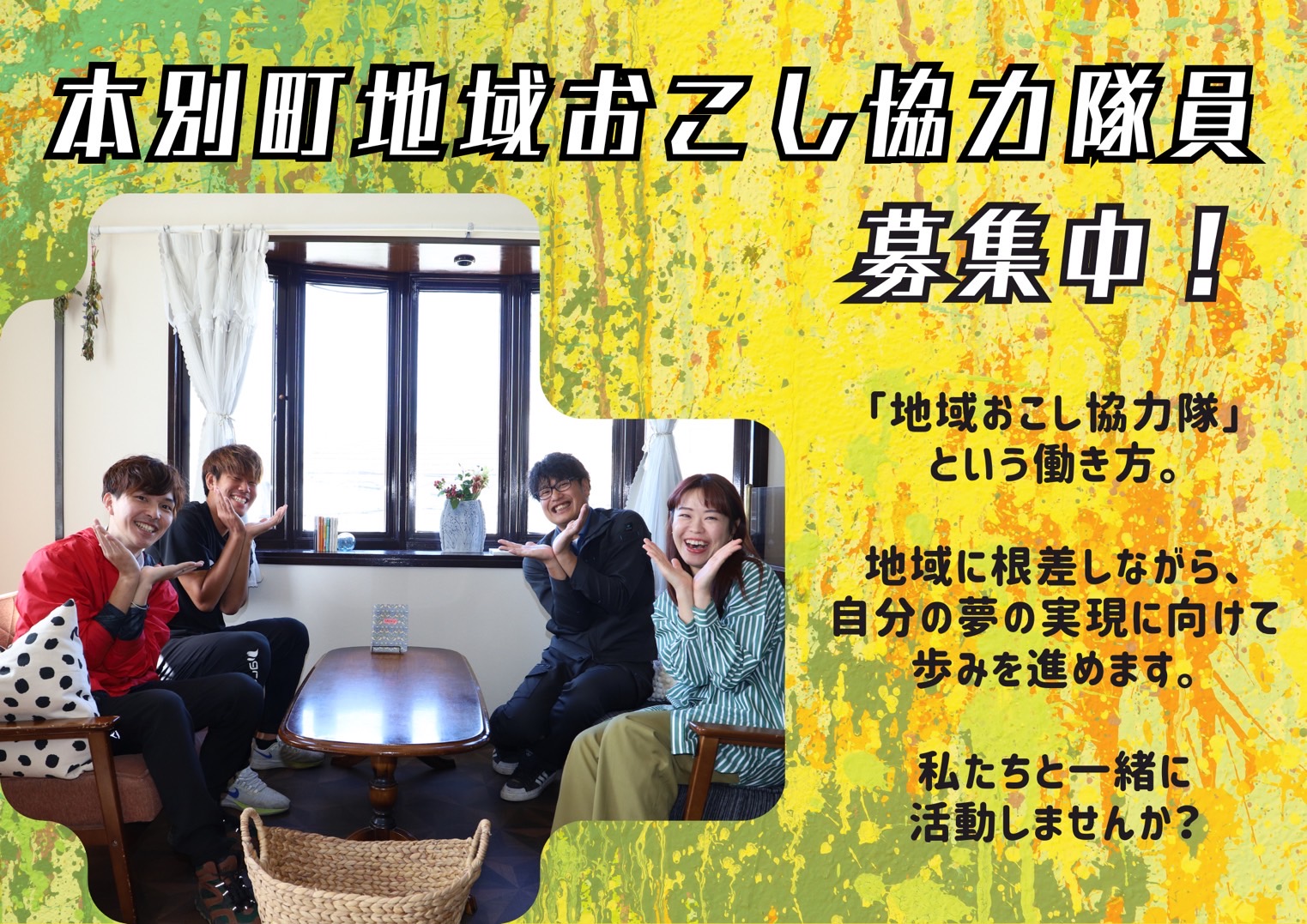とかち創生学に参加してきました!

みなさんこんにちは!情報発信推進員の福川です!
4月23日とかち創生学に参加してきました!
1.「とかち創生学」とは?
「とかち創生学」とは、北海道本別高校の総合的な探究の時間として行われている取り組みです。
平成 31 年4月より、①正解のない課題に挑戦し探究し続ける力の育成、②次世代の十勝をけん引し地域を支える力の育成、③グローバルな視点をもって地域を支える人材の育成、を目標として、【総合的な探究の時間「とかち創生学」】が開始されました。
こちらの取り組みで出たアイディアが「地学協働アワード2023」のグランプリを受賞したこともあります。
2.1年生の授業に参加!
ぼくは、今回1年生のとかち創生学に参加してきました。入学からまだ3週間と日は浅いですが、みなさん大分慣れてきた様子で、爽やかな笑顔であいさつしてくれました。
授業では、初めにSDGsの説明をしたのちに、実際に国連で行われた「2030 SDGs」というカードゲームを行いました。
このカードゲームは、2030年までにSDGsの目標を達成するために、多種多様な文化や歴史を持つ人々がいるなかで、どのような取り組みをすればよいか、私たちに必要なことは何なのかを。体験的に学ぶことができます。
ぼくも生徒たちと一緒にこのゲームをやってみました!
3.ゲーム前半
このゲームのルールを説明すると長くなってしまうのですが、簡単に話すと「それぞれの班(→国)の目標を2030年までに達成する」ことがゴールになります。目標は班によって違い「お金」「時間」「プロジェクト」等の要素を使って、「世界の状況」に配慮しながら達成に向けて行動をする、というものでした。
時間が限られていたので、ゲームが開始すると同時に各班が一斉に目標達成のために動き出しました。しかし、自国の利益ばかりに目がいきがちになってしまい、「世界の状況」は極端になってしまいました。
この「世界の状況」は「経済」「環境」「社会」の三つの分野で構成されており、それぞれパラメーターで表されます。それぞれの班(国)がそれぞれのプロジェクトを行うと、このパラメーターの値が減ったり、増えたりします。
パラメーターはそれぞれの値が3でスタートするのですが、前半終了時点で「経済」が25、「環境」が4、「社会」が5となっていました。これは「経済はめっちゃいいけど、市環境と社会はめちゃめちゃ悪い」という状況です。
先程「目標は班によって違い」と書きましたが、実はすべての目標には一つだけ共通していることがあります。それは「2030年(ゲーム終了時点)のとき豊かな世界に生きている」ということです。
つまり、この時点では豊かな世界に住んでいるとは言えませんでした。
4.ゲーム後半
後半戦開始。前半終了時点の総括を受けて、各班の動きが変化します。前半時点で目標を達成したチームは2つありましたが、彼らは豊かな世界を作るために動き出します。まだ目標を達成できてないチームのサポートを始めました。ここで目標達成したチームが、また別のチームのサポートに動く連鎖が起こりました(ぼくがいた班はお金を無料で配っていました)。
最終的には、すべての班が協力して豊かな世界を作るために行動をしました。
5.結果発表
各班の協力プレイもあって、ゲーム終了時点には「世界の状況」がとてもバランスよくなりました!
全チーム目標を達成し、無事、豊かな世界に住むことができました!
と思いきや、
まさかのハプニング!
前半時点で目標を達成していたチームがなぜかゲーム終了時点では未達になっていました。しかし、そこには、自己犠牲を出してまでほかのチームのサポートをした、という背景がありました。
まさかの事態がありましたが、このゲームを通して、2030年SDGs目標を達成するためにどうすればよいかを生徒一同(福川含む)が身をもって学びました。
6.感想
めちゃめちゃ楽しみにしていた「とかち創生学」でしたが、期待以上に楽しい授業でした!おそらく生徒以上に楽しんでいましたね(笑)。今回行ったカードゲームは大人から子どもまで、みなさんが楽しみながらSDGsについて学べるものだと感じました。
また、生徒たちの積極的な姿勢に感動しました。特にゲーム後半、誰かに言われたわけでもなく、自発的にほかのチームと協力したり、少しでも豊かな世界にするために行動する姿はとても素敵でした。この主体性や思いやる気持ちの積み重ねが、SDGs達成に向けて必ず必要になると感じました。SDGsに限らず、社会という集団において必要な力をすでに本別高校一年生の若人たちは持ち合わせているのだと実感しました。
SDGsについても理解を深められ、これからの本別町、日本を担う素晴らしい高校生たちとも交流ができ、大変貴重な時間を過ごせました!
最後までご精読いただき、ありがとうございました!